検討項目
| 位置 |
検討する部分 |
種別 |
訂正案, コメント |
| P.38 L.3 |
同様に..(中略)..どれかを要請することによって同じことが可能である。逆向きの条件は必要ない。 |
Y1 |
あるいは,逆向きの意味を除いて,単に..(3つの数式)..といった要請をしてみてもよい。
|
-
該当部分の原文は,
We can, alternatively, merely require that x#Ry
→ xRy, or that x#Py→xPy, or that x#Iy→xIy, without the converse implication. となっています(#は上のバーの代わりに使いました)。
- そこで,反対向きの矢印を除いて,単にこんなことを要求してみてもよい,といった程度のニュアンスかと思われます。例えばx#Ry→xRyであれば,xRyの詳細は不明だけれども,とにかくx#RyのときはxRyということにするということです。
-
ここで和文を「同じことが可能である」とすると,前の部分とのつながりから「集合的選択ルールを導くことができる」(集合的選択ルールの定義)と読めてしまう心配があります。
- 今回は⇔でなく→ですから,集合的選択ルールの定義ではなく,集合的選択ルールの条件といった程度のものと思われます。(つづく「ルールそのものというよりは,集合的選択ルールの条件である」という表現の意味もそのように理解してよいかと思います。)
-
集合的選択ルールを「定義」するためにはxRyの意味を確定させる必要があります。つまり,「xRy⇔...」の...の部分を確定させる必要があります。(訳書のP.39の下部の議論も参考になります。)
|
|
本ページの概要とお願い:
- 本ホームページは,Amartya Sen先生の『集合的選択と社会的厚生』(日本語版, 勁草書房)の
特定の記述項目について,読む上でのポイントを考えるものです。
-
本ホームページの主旨や注意などについては,こちら(「読解のポイントを探る」項目リストページ)をご覧下さい。
|
|
[2013年7月23日 初版をアップ]
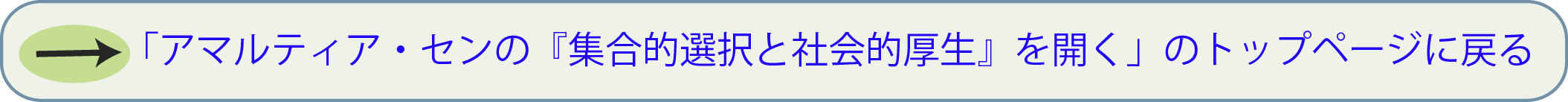
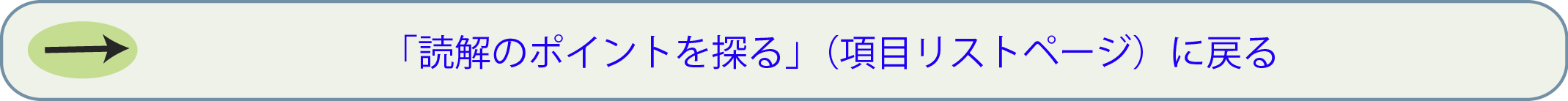
|